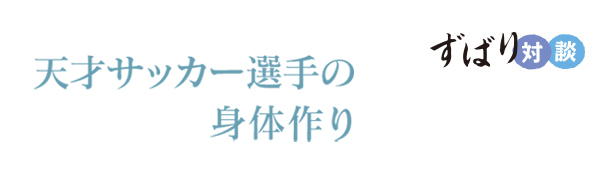

わずか13歳でU-16日本代表選手となり、プロデビュー後たった10日で日本代表メンバーに選出。日本史上最年少の18歳でFIFAワールドカップフランス大会本戦に出場。以来、通算3回日本代表としてW杯に出場、Jリーグのほか3つの海外チームでも活躍し、2023年に現役を引退。「天才」と呼ばれた稀代のサッカー選手、小野伸二さんと田中靖人先生との対談は、小野さんの意外な食習慣の話題から始まりました。
(2025年4月14日収録)
食べたら食べた分、動けばいい
田中
私は消化器内科の中でも肝臓の疾患を専門としています。肝臓の健康は食生活や肥満の影響が大きいので、いつも患者さんには「3食バランス良く、朝食もきちんと食べるように」と伝えています。ところが小野さんは現役時代、ずっと1日1食生活だったそうで、驚きました。
小野
中学時代に栄養士さんから「朝食は1日の運命を決めるというくらい大事だ」と教えていただき、それを日常に活かしていましたが、28歳頃からは1日1食生活になり、ほかの選手ほど徹底した食事管理をしていたわけではありませんでした。その日に食べたいものは人それぞれ違うのではないかと思って、自分自身がその日に欲するものを食べるようにしていました。
田中
1日1食生活を始められたのには、何かきっかけがあったのですか。
小野
移籍先のドイツでの単身生活で、正直、朝ぎりぎりまで寝ていたいというのもあって朝食抜きを始めたのですが、慣れると朝食抜きのほうが集中できるし、調子がいいと気づいたのです。逆に食べてからトレーニングするとぼーっとしてしまう。エネルギーは入っているはずなのに、集中力に欠ける自分がいたりしたのです。それで、朝食は僕には合っていないと思ってやめ、昼食を食事のメインとしてたくさん摂るようにしました。朝はブラックコーヒーを飲んで、トレーニングして、だんだんおなかが空いてきて、昼をしっかり食べる。野菜、お肉、ご飯などの炭水化物。食事の中でお肉は鶏が一番好きなので、鶏を使った料理をよく食べていました。脂質はそれほど気にしないので、唐揚げを食べるときもあります。
田中
一般的には3食バランス良く摂っていないと、どこかで多くの量を食べてしまうので肥満になりやすいのですが、小野さんほどの運動量があれば問題ないのかもしれませんね。
小野
結局、食べたら食べた分、動けばいい。僕らは日常的に運動しているのでそれができますから。逆に夜はエネルギーをそれほど消費しないので、外食などの予定がなければ一切食べないときもあります。練習中や空腹を感じたときには、日常的に炭酸水を飲んでいました。海外だと食文化の違いもあって、たとえばオランダでは試合の当日や前日にチームのビュッフェで大きいステーキが出されていました。温野菜とライスとサラダ、スープ、デザートが出て、食べるものも量も個々の選手に任されています。日本では試合前に脂っこいものは避けるとか、前日までに炭水化物を多く摂ったほうがいいとか言われていて、鶏肉、特にささみがよく出ます。確かに鶏のほうが消化にいいのかもしれないですが、ステーキをパワーに変えられる選手もいます。日本では試合前日は飲酒をしないほうがいいと言われますが、ドイツでは夕食が終わって2時間後のミーティングの際に、試合前日でもサンドウィッチとビールが出ます。これには僕も最初はびっくりしましたが、こういった海外での経験をきっかけに、一律に「〇〇を食べたらだめ」と決められたことに従うのではなく、自分の体質や生活習慣に合った食生活でいいのではないかという考えに変わりました。
ワールドカップ直前に虫垂炎を発症
田中
ところで1999年のシドニー五輪予選では、左膝のじん帯断裂という大けがをされました。復活のためのリハビリは大変だったでしょう。
小野
リハビリとして行うトレーニングは普通の練習より数倍きついのです。特に1990年代はリハビリやトレーニング、食事についての知識がまだ十分ではなかった時代です。だから根性論ではないですが、「とにかくやろう」みたいなリハビリでした。たとえばベンチプレスや筋力トレーニングをたくさんこなした後に、手で自転車を漕ぐというメニューがありました。高いワット数*1を維持したまま1回4~5分間速く漕ぐ。それを4セットくらいやるわけです。しんどすぎて呼吸もできないぐらい苦しい。正直、吐きながらやっていたくらいに自分を追い込んでいました。これが嫌だからスポーツ選手は怪我をしたくないのです。それによって強い身体を作れた部分もあるので後悔はないですが、本当にきつかったですね。当時4人ぐらいの選手が同じようなトレーニングをしていて、彼らに笑わせてもらって、盛り上げながら励まし合っていました。その人たちがいなかったら、僕はあのリハビリを乗り越えられなかったと思います。
田中
サッカーボールも触らずにやるわけですからね。それもストレスですよね。
小野
それが苦痛でしたね。だからトレーナーさんに見られていないときにこそこそ触っていました(笑)。
田中
2002年のFIFAワールドカップの本大会直前には虫垂炎*2にかかって、それでもワールドカップ出場を果たされましたね。
小野
数日にわたり微熱が続き、胃の痛みが日に日に強くなって右下に拡がっていきました。出場選手発表の直前に病院で虫垂炎と診断され「今すぐ切除を」と言われたのですが、手術を受ければワールドカップには出られなくなります。お世話になっている医師を通じて「どうにかなりませんか」と別の消化器病の先生にお願いしたところ、「もしかしたら点滴だけで散らせるかもしれない。試す価値はあると思う」とおっしゃったので、3日間入院して点滴を受けました。虫垂の腫れはかなり大きくて、もうすぐ合併症となる危ない状態だったのですが、痛みがやわらいだので試合に出て、ワールドカップの直後にまた入院して手術を受けました。その後は一切、後遺症はなかったです。
田中
本当に良かったです。虫垂炎から腹膜炎を合併する方はまれにいらっしゃいます。腹膜炎を起こすと手術後に癒着しやすくなり、その後も食事を摂りすぎると腹痛が起こるなど、食生活にも響くのです。
しっかり食べて運動すれば、腸も動く
田中
現役を引退された後も1日1食を続けているのですか?
小野
いや、今は普通に3食食べています。特に引退後はご飯がおいしくてしょうがないです(笑)。ただ、現役を終えて運動量が減ると、その分がはね返ってくると感じています。だから若干控えますが、食べたいものを食べないと、逆にそれがストレスになります。その日に食べたいものを食べて、ストレスをためない毎日を過ごしたいのは現役時代と変わりません。
田中
ストレスをためないことは体調管理にもとても大事なことで、それも小野さんが長く選手生活を続けられた秘訣なのかと思います。そして、ご飯をしっかり食べるのはとても良いと思います。病気治療のために糖質制限が必要な人は別ですが、太るからという理由で炭水化物を避けてタンパク質だけを摂る、いわゆる「糖質制限ダイエット」はよくありません。米に含まれる食物繊維も摂れませんし、食べたものをエネルギーに換えるにも糖質は必要です。食べて運動すると、腸が動きます。運動不足は肥満にもなりますが、便秘にもなり、腸の健康状態も決して良いとは言えません。
小野
現役時代は気にしなくても体重を維持できていたのですが、最近は「やばい。走りに行かなきゃ」と意識するようになりました。仕事の空き時間を見つけて5~7km走るようにしていますが、走るというのは大変です。ボールがあれば走るのですが、ボールがないともう走れません(笑)。
子どもたちに「自分から考える」大切さを伝えたい
田中
現在、小野さんはJリーグ特任理事として、全国の小学生にサッカーや環境の大切さを教えておられます。室内でゲームなどを長時間やる習慣がある子は屋外に出たくなくなって肥満になりやすい。動かない子どもたちがどうすれば外で遊んでくれるのでしょうか。子どもの肥満がとても増えており、このままいくと肥満症大国になってしまうことを心配しています。
小野
今、ボールの使用が禁止されている公園が増えていますが、子どもたちが外で遊ぶ場所が減ってしまったことは考えなければいけないのではないかと。僕自身は公園でボールを使うことをむしろもっと推奨してほしいと思います。サッカー教室も子どもたちが自分から率先して、ボールを使って外で遊びたいと思うきっかけになればと思いながらやっています。これはJリーグの総勢60クラブの協力で、各地のクラブチームのレジェンド選手たちにも協力してもらって教えているのですが、小学生にサッカーの楽しさを伝えることはもちろん、「やらされているのではなくて、やりたいから行く」という気持ちを持ってもらいたいという思いがあります。今の小学生はいろいろな面で大人たちから与えられ過ぎていて、自分から学び、吸収したいという欲求が少ないのではないかと考えています。僕が子どもの頃は週2回しかトレーニングがなかったので、早くその日が来ないかなと毎日一生懸命に練習していました。サッカーも2人いれば野球のキャッチボールのようなこともできるし、壁があれば1人でも練習できる。自分から考えて何かをしようという意思があれば何でもできます。子どもたちの前で自分が良いプレイを見せて、自分から学ぼうと思えばいろいろなことができるんだよ、とみんなに伝えたいと思っています。
田中
今日は憧れの小野選手にお会いできて、楽しいお話をお伺いしました。2026年はワールドカップイヤーでもあります。小野さんにはこれからも子どもたちを含め、我々市民にもスポーツ文化を広げるためにさらにご活躍いただきたいと思います。ありがとうございました。
【欄外注】
*1 ワット数:自転車漕ぎのパワー出力(仕事率)を表す単位。
*2 虫垂炎:昔は「盲腸炎」と呼ばれていたが、19世紀末に盲腸の先端にぶらさがっている虫垂の炎症がこの病気の本質であることが明らかになって以来、「虫垂炎」と呼ばれている。

構成・中保裕子






